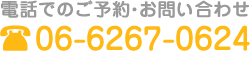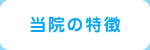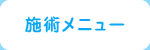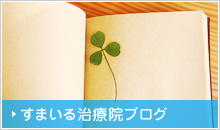こんにちわ!今回は肩関節の動きをサポートするテーピングです。
この貼り方は、以前ブログで書いた五十肩の治療としてもよく使います。五十肩の人は一度やってみてください!貼るだけで痛みが軽減すると思います。
①テープをY字に切り三角筋のふくらみの終わったところの上にテープの切れ目がくるようにテープの一端を貼ります。

②腕を後ろに引き、前腕の筋肉を包み込むように貼ります。

③後ろのテープを貼るときには腕を前に抱かえるようにし、後ろ側の筋肉を包み込むように肩まで貼ります。

④完成です。三角筋を包み込むように貼れているか、確認してください。

これらの上半身安定テーピング1・2・3と以前、ランナーのためのテーピング2で書いた腰痛テーピングをあわせて貼ってトレーニングすることで姿勢が安定しいろんな筋肉が効率よく使えるようになり、身体意識も高まります。
今年も残りわずかですが皆様にはいろいろお世話になり、ありがとうございました。皆様のご健康を心よりお祈りします。良いお年をお迎えください。来年も宜しくおねがいいたします。 すまいる治療院 間林五郎

日本海の夕日
まず、肩こりなど起こす僧帽筋を保護することにより、肩甲骨の位置を安定させます。
肩甲骨が前方へ動き過ぎて固定されることで猫背になりやすくなるのでテーピングによって後方への動きを補助します。
(僧帽筋テーピング)
①テープをY字に切り肩峰下より貼り始めます。

②首を反対側に側屈させテープを引っ張らずに毛の生え際まで貼ります。

③下のテープを肩甲骨に沿って背骨までテープを引っ張らずに貼ります。

このテーピングを日常的に貼ることで肩甲骨の可動域が増えます。肩のこる人は是非試してください!すまいる治療院では施術後よく貼ります!
次回、肩周り(三角筋)・腕が上がりやすくなるテーピング予定です。よろしくおねがいします。
久々の投稿です。今回は上半身を安定させるテーピングです。
上半身を安定させることにより各関節痛の予防や安定することで複数の筋肉が効率よく使え筋肉疲労を軽減させパフォーマンスの向上につながります。
また、胸郭(肋骨)の可動域も広がることで呼吸が楽になり運動の持続力もアップします。運動のみならず仕事での肩こりや五十肩・首の痛みなどにも有効なので施術後に貼ることも多いです。
胸郭運動

次回、簡単にできる貼り方かきます、よろしく。
本日、足首保護テーピング
使用するタイミングは運動15~30分前または、ハーフタイム、レース後半で足首の「痛み」や「不安感」が気になる前に、なるべく早めに使用してください。

① 5cmはばのテーピングで上図のテーピングを作成。
A(約15cm)・B(約30cm)・C(約50cm)
Aのはくり紙をはがし、粘着面を上にして床(地面)に置きます。Bを引き上げたとき、内(外)側のくるぶしの真上を通るよう、足ウラをAの部分にのせます。

② 足首の角度を90度に保った状態で、Bのはくり紙をはがし、内(外)側のくるぶしの真上を通過させながら、まっすぐ上にのばして貼ります。もう一方のBも同じ要領で貼ります。

③ ②と同様に足首の角度を保ったまま、片側のCのはくり紙をはがして、足の甲を通します。

④ 反対側のくるぶし、アキレス腱を通過しさせます。

⑤ 足首に巻きつけていき、貼ります。

⑥ もう一方のCのはくり紙をはがして、同様に貼ります。

⑦ これでできあがりです。あまり強くしめすぎると、血行障害や皮膚障害の恐れがありますのでご注意ください。

⑧ 反対からみると、このようになります。

このテーピングはランニングのみならず、バレーボール・バスケットボールなどでジャンプ後の着地動作を安定させ、ケガ予防にも役立ちます。また、ネンザなどの応急処置や痛み軽減・回復促進にも効果あります。(テーピングの上からシップを貼ってもOK)
是非、おぼえて下さい!
本日、踵や足の裏の痛み防止のテーピングです。
足骨は多くの関節のなかでも特に複雑でブロック状の骨が複雑に結合され、それぞれが関節となります。そのため足の裏の縦横アーチとなり体重を支えています。

足の裏には、足底筋膜と呼ばれる、膜のように薄く幅広い腱が、かかとの骨から足指の付け根まで張っています。足の甲の骨は、弓状(アーチ)になって体重を支えているが、アーチを弓の弦のようにピンと張って支えているのが、足底筋膜です。

丈夫な足底筋膜も、歩行やランニング、ジャンプで使いすぎたり四十歳代以降になると、古いゴム管のようにひびが入り、炎症を起こします。それが痛みの原因となります。長引くと、足底筋膜の付け根にあるかかとの骨が、とげのように大きくなり、痛みが増すこともあります。ランニングなどの過使用による緊張以外には、へん平足、老化によるアーチの低下なども原因となります。長距離走をはじめとしたスポーツのほか、長時間の立ち仕事をする人も発症します。
いろいろ貼り方はありますが、基本的な足低テーピングです。
①テープを熊手状(4本)に切り、テープの一端をかかとの付け根から貼り始めます。

②1本づつ指と指の間に向かって貼って行きます。完成です。

踵の保護テープ
①足の裏側にアンカーテープを貼るA。Aのアンカーテープの内くるぶしの下からアキレス腱の下、外くるぶしの下を通してアンカーテープを貼るB。(2.5cm幅テープ使用)

②①を交互に繰り返して行う。

③かかとの部分をしっかり覆う。

④①のBのアンカーテープの上にアンカーテープを貼る。

完成。
足の正常なアーチ

ついでに、足低ストレッチ

だらだら・・・ながくなりましたが、足低筋膜とアーチは長距離ランナーにとってとても重要なので保護してください。
次回、足首保護テープ予定です。よろしく!
ランナーに限らず、スポーツ愛好家に多いのが肉離れ(ふとももの後ろ)です。
ここは、ハムストリングといい大腿二頭筋・半膜様筋・半腱様筋の3筋で構成され足の動き作りや運動能力に大きく影響する部分とされます。

(ハムストリングの保護テーピング)
①テープをY字に切り前屈した状態でお尻の付け根から膝裏上5cmのところに切れ目がくるようにテープを引っ張らずに貼ります。

②両端部を膝裏の関節にかからないように内外側部に貼ります。

③完成です。お尻の付け根のところにテープのシワが入ります。

肉離れは1度なると癖になるのでしっかり保護しましょう!
ついでに、かんたんな腰痛テーピング(体幹部・腰部の安定)
①テープをY字に切り、前かがみになり、仙骨よりテープの一端を貼ります。

②前屈した状態でテープを引っ張らずに背骨の両側の筋肉に沿って貼ります。

③完成です。上体を起こした時にテープにしわが入ります。

これは、脊柱起立筋・腰方形筋・大腰筋・後背筋といった腰周りを支える筋肉をサポートし、各スポーツのパフォーマンスを高めます。腰痛時の治療効果もあります。
次回、かかとや足の裏のテーピング予定です。
本日、ランニングで有効なテーピングいきます!
マラソンの練習時や本番で、ひとによって関節のくせがあるので痛みに出る場所がいろいろあります。弱い場所や負荷の多い場所にテーピングし異常な動きを正常な動きに戻します。貼って動いてるだけで治療にもなります。
(足首・ふくらはぎ・ヒラメ筋・アキレス腱)
① テープをY字に切り、かかとを浮かし、アキレス腱を伸ばした状態で、土腐まずからかかとを包むように貼り始めます。

② 両端のテープでふくらはぎを包み込むように貼ります。

③ 完成です。かかとを浮かせた時に足首にテープのシワが入ります。

(基本的な膝の保護)
① テープをY字に切り、腰骨の付け根から貼り始め、テープの切れ込みが、ひざ上にくるようにテープを引っ張らずに太ももに貼ります。

② 膝を曲げた状態で、切れ込みが入っている一方のテープを外側からお皿を包み込む様に貼り、もう一方のテープを同様に内側からお皿を包み込む様に貼ります。

③ 完成です。

(さらに補強が必要な場合)
① 膝を曲げた状態でお皿を下から支えるようにU字状にテープを貼ります。

② 完成!

(過度の運動で膝の外側が痛む)
① 腰骨より貼り始めひざ外側の下までテープを引っ張らずに筋肉を伸ばして貼ります。

これは、股関節痛保護にもなります!
(膝の内側が痛む)
膝内側はふともも前面の筋肉群の腱が膝内側を通って膝下(下腿の内側)に付着しており、その部分をガソクといいます。痛みは、女性に多いです。

上図の部分をテープで補強します。
基本的な貼り方ですが、いろいろ組み合わせます。貼って運動すると以外ときもちいいです。ためしてみてください!
最近、ゴルフ・テニス・マラソンなど、スポーツをする人が増えているのでテーピングについて書きます。

テーピングには用途・目的別でいろいろありますが、大きくわけると基本的には2種類でホワイト・テープ(固定テープ)とキネシオロジー・テープ(伸縮テープ)に分かれます。
(ホワイト・テープ) 固定だけを目的にしており、コンタクトスポーツなどハードにぶつかり合うプレーの際に、関節を固定して補強し怪我を予防するために使います。また、負傷後の固定に使うこともあります。


(キネシオロジー・テープ) あるていど固定はしたいが柔軟性もほしいというニーズに加え筋肉にそって皮膚上に貼ることで正常な動きにサポートし運動や仕事などからくる慢性痛など防ぎます。また、リンパの流れを刺激するので疲労を軽減・回復するといった効果もあります。こちらのほうが用途はひろいです。


次回、スポーツ別貼り方を紹介します。よろしく!
大阪介護支援協会 西区支部、研修会に参加。
高齢者や要介護者が住み慣れた地域で生活が継続できるよう、在宅医療と介護との連携への推進にむけてがテーマ。
今回は、永田医院・永田昌敬先生が主治医への情報提供で必要なことやアセスメント・連絡、連携方法・糖尿病患者についてなど講義されました・・・大変、勉強になります。
その後、懇親会へ・・・・。西区支部長・北堀江病院 福嶋氏のあいさつ。

残暑お見舞い申し上げます。
日中はまだまだ、あついですが・・・めげずに頑張りましょう!
皆様の健康をお祈りしております。

西区の風景